早稲田大学 森林保全研究会
研究会の活動方針
森林保全研究会では、国内外の森林等の土地利用分野を研究対象とし、その持続性を担保することを目的といています。このため、喫緊の課題である地球温暖化対策に貢献すること、さらに対策事業を社会実装するための活動を進めています。研究会の事務局を森林環境科学研究室が担当しています。
キーワード: 地球温暖化対策(温室効果ガスの排出削減・吸収)、持続可能な開発目標(SDGs)の社会実装、熱帯林保全、里地・里山の保全・活性化、農村開発、生物多様性の保全
途上国での熱帯林保全の研究
国外では、ラオスやミャンマー等の東南アジアの熱帯林を対象に、森林減少・劣化の抑制(REDD+)の実施に係る研究成果の社会実装を目的にしています。REDD+に係る制度設計、実施のための諸課題への対応等、様々なテーマに取り組んでいます。詳細は以下をご覧ください。
国内での里地・里山保全の研究
里地・里山を対象に、とくに二次林とそれと連続する農地や宅地等を含めたランドスケープレベルでの保全を研究テーマにしています。里地・里山への人間活動の影響が大きく変化する中、将来の里地・里山の保全方法を提案するため、包括的に取り組んでいます。詳細は以下をご覧ください。
途上国での熱帯林保全の研究の概要
熱帯林の減少・劣化が顕在化し、すでに十数年が経過しています。しかし、今なお熱帯林の減少・劣化が続いているのが現実です。そうした中、多くの途上国でREDD+が進められています。一方でREDD+への多様な主体の参加、REDD+の効果的な実施、REDD+の成果を見える化する方法等々、多くの課題が残されています。森林保全研究会では、そうした諸課題への対策提示を進め、さらにREDD+の社会実装を後押しすることを目的にしています。



主な研究対象地: ラオス北部、インドネシア南カリマンタン州&西カリマンタン州、ミャンマー中部
研究・社会実装の方向性
ラオス北部のルアンプラバン県でREDD+プロジェクトを実施しています(研究成果の社会実装)。当初、REDD+は期待通りには進みませんでした。とくに、幅広いステークホルダー(とくに民間事業体)の参加が進んでいませんが、その原因を特定しつつ、どのように対処して今後に繋がていくか取り組んで決ました。森林保全研究会ではREDD+の優良プロジェクトを構築・実施し、そこで蓄積する知見・経験を取りまとめることが最大の目的です。
研究・社会実装の進捗・成果
ラオス北部で進めたREDD+プロジェクトについて、日本とラオスが進める二国間クレジット制度(JCM)の下での事業化を進めています。進捗はこちらをご覧ください(JCM-REDD in Lao PDR)。
また、2015年から始まった持続可能な開発目標(SDGs)とREDD+とのシナジー効果について、その見える化に取り組んでいます。森林保全研究会ではSDGsの各ゴールとREDD+の頑強性が結び付いており、多くが相乗効果をもたらすというコンセプトを取りまとめました。
その他
途上国での熱帯林保全の研究は、以下の助成で進めました。感謝申し上げます。
令和元年度「途上国におけるGHG排出削減 ・ 吸収量のモニタリング技術及び森林減少 ・ 劣化対策としての村落活動の普及活動(一般社団法人 日本森林技術協会」
国内での里地・里山保全の研究の概要
里地・里山を対象に、とくに二次林とそれと連続する農地や宅地等を含めたランドスケープレベルでの保全を研究テーマにしています。里地・里山への人間活動の影響が大きく変化する中、将来の里地・里山の保全方法を提案するため、包括的に取り組んでいます。



主な研究対象地: 石川県能登町、埼玉県所沢市・三芳町、埼玉県小川町、長野県北相木村
研究・社会実装の方向性
国内に広く分布する二次林は、人間活動により成立し、人間活動によって維持されてきました。その結果、日本は国土の約70%程度が里山・里地となっています。一方、直近70年程度で急速に里山(二次林)の利用方法が変化してきた結果(二次林における人間活動が直接的・間接的に変化してきた結果)、身近な自然環境としての二次林が大きく変化しようとしています。そうした中、『将来の二次林のあり方』について包括的な視点から研究を進めています。
研究・社会実装の進捗・成果
作成中
その他
国内の里地・里山保全の研究は、以下の助成で進めました。感謝申し上げます。
令和元年度「能登半島の中山間地域における地域住民と交流住民との連携による活性化モデルの構築」(緑と水の森林ファンド)(公益社団法人 国土緑化推進機構)
令和2年度
「能登半島の中山間地域における住民グループと都市住民の連携による地域活性化・グリーンビジネスのモデル構築」 (緑と水の森林ファンド)(公益社団法人 国土緑化推進機構)
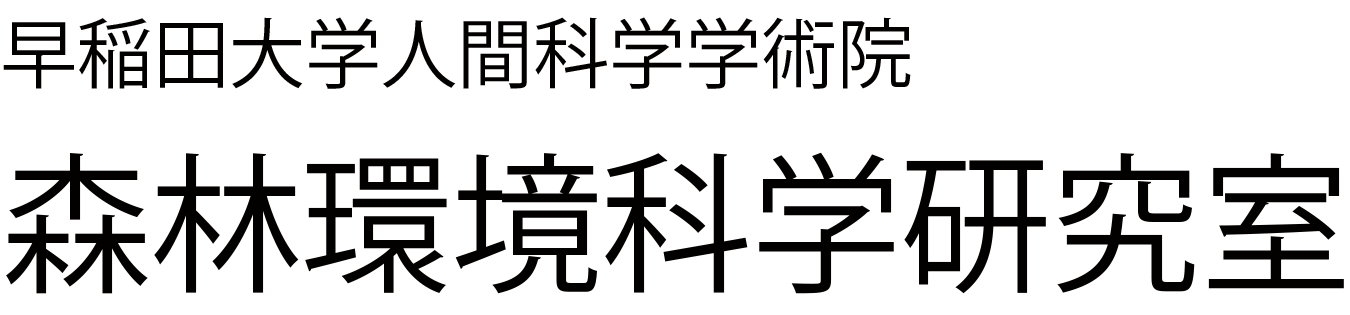
 HOME
HOME